
1日目:ショット練習

2日目:アプローチ、パター練習

4,5日目:コースラウンド 男女とも初心者はピンクティより
 松林幸一郎(まつばやし・こういちろう)
昭和31年東京都生まれ
学習院高等科卒業
昭和54年東海大学体育学部社会体育学科卒業
昭和54年亜細亜大学教養部 助手
昭和61年亜細亜大学教養部 講師
平成6年亜細亜大学教養部 助教授
平成15年亜細亜大学経済学部 助教授
平成19年亜細亜大学経済学部 准教授現在に至る
3歳よりスキーを始め、高校よりスキー競技に夢中になり現在に至っています。ゴルフは夏休みの2週間ほど高校1年より大学3年まで軽井沢72にてキャディーのアルバイトをし、覚えました。
当初は止まったボールを打って何が面白いのか全く理解ができませんでしたが、いざコースをまわるとボールが飛んだ時の爽快感、アプローチの難しさなど魅力に引き込まれていきました。
現在は用具を使うスポーツで、如何にして用具を上手に使用できるかを指導することに興味を持っています。
担当科目
スキー、ゴルフ、バドミントン、バレーボール、テーマ研究
全日本スキー連盟公認指導員 全日本スキー連盟公認A級検定員
全日本スキー連盟公認パトロール 日本赤十字救急・救助員
専修大学、駿河台大学 非常勤講師 ゴルフ授業担当※この記事は掲載元(月刊ゴルフ用品界 GEW)の許可を頂いて転載しています。
掲載元 月刊ゴルフ用品界 9月号(見本誌の申し込みはこちらから)
松林幸一郎(まつばやし・こういちろう)
昭和31年東京都生まれ
学習院高等科卒業
昭和54年東海大学体育学部社会体育学科卒業
昭和54年亜細亜大学教養部 助手
昭和61年亜細亜大学教養部 講師
平成6年亜細亜大学教養部 助教授
平成15年亜細亜大学経済学部 助教授
平成19年亜細亜大学経済学部 准教授現在に至る
3歳よりスキーを始め、高校よりスキー競技に夢中になり現在に至っています。ゴルフは夏休みの2週間ほど高校1年より大学3年まで軽井沢72にてキャディーのアルバイトをし、覚えました。
当初は止まったボールを打って何が面白いのか全く理解ができませんでしたが、いざコースをまわるとボールが飛んだ時の爽快感、アプローチの難しさなど魅力に引き込まれていきました。
現在は用具を使うスポーツで、如何にして用具を上手に使用できるかを指導することに興味を持っています。
担当科目
スキー、ゴルフ、バドミントン、バレーボール、テーマ研究
全日本スキー連盟公認指導員 全日本スキー連盟公認A級検定員
全日本スキー連盟公認パトロール 日本赤十字救急・救助員
専修大学、駿河台大学 非常勤講師 ゴルフ授業担当※この記事は掲載元(月刊ゴルフ用品界 GEW)の許可を頂いて転載しています。
掲載元 月刊ゴルフ用品界 9月号(見本誌の申し込みはこちらから)

テニスコートでのパッティング練習風景

打撃練習の風景
 松井健(まつい・たけし)
1963年新潟県生まれ。早稲田大学教育学部教育学科体育学専修卒業。順天堂大学大学院修士課程体育学研究科修了(体育学修士)。
川崎医療福祉大学大学院博士課程:医療技術学研究科修了(博士:健康科学)。中京大学(実験実習助手)、吉備国際大学(助手、講師)、日本福祉大学(准教授、教授)を経て、2014年追手門学院大学に着任。
基盤教育機構教授、スポーツ研究センター長。基盤教育科目の「基礎体育(実技)」「応用体育(実技)」「体育概論」の他、スポーツキャリアコース科目の「スポーツ生理学」「高齢者スポーツ論」を担当。担当する実技種目は、ゴルフの他、フライングディスク、卓球、ボッチャ、テニスなどである。
体育実技の授業ではチームでのグループワーク手法を用いて履修生のコミュニケーション力を高め、積極的な活動となることを目指している。また、すべての講義系、実技系授業において毎回のレポートを通じた履修生とのコメント交換を行っている。
高齢者を対象としたトレーニング研究や地域貢献につながる取り組みを行っている。また、アメリカンフットボール部の部長を務めている。
所属学会は、日本体力医学会、日本体育学会、日本運動生理学会、日本水泳水中運動学会など。日本水泳連盟理事(科学委員会所属)、愛知水泳連盟理事(医科学委員会所属)。
松井健(まつい・たけし)
1963年新潟県生まれ。早稲田大学教育学部教育学科体育学専修卒業。順天堂大学大学院修士課程体育学研究科修了(体育学修士)。
川崎医療福祉大学大学院博士課程:医療技術学研究科修了(博士:健康科学)。中京大学(実験実習助手)、吉備国際大学(助手、講師)、日本福祉大学(准教授、教授)を経て、2014年追手門学院大学に着任。
基盤教育機構教授、スポーツ研究センター長。基盤教育科目の「基礎体育(実技)」「応用体育(実技)」「体育概論」の他、スポーツキャリアコース科目の「スポーツ生理学」「高齢者スポーツ論」を担当。担当する実技種目は、ゴルフの他、フライングディスク、卓球、ボッチャ、テニスなどである。
体育実技の授業ではチームでのグループワーク手法を用いて履修生のコミュニケーション力を高め、積極的な活動となることを目指している。また、すべての講義系、実技系授業において毎回のレポートを通じた履修生とのコメント交換を行っている。
高齢者を対象としたトレーニング研究や地域貢献につながる取り組みを行っている。また、アメリカンフットボール部の部長を務めている。
所属学会は、日本体力医学会、日本体育学会、日本運動生理学会、日本水泳水中運動学会など。日本水泳連盟理事(科学委員会所属)、愛知水泳連盟理事(医科学委員会所属)。

グラウンドでの打球練習の様子

スナッグゴルフのラウンドの様子

グラウンドでの打球練習の様子
 鶴原清志(つるはら・きよし)
1956年福岡県生まれ。1979年筑波大学体育専門学群卒業。1984年筑波大学体育科学研究科(博士課程)中退。1984年名古屋大学総合保健体育科学センター助手。1986年三重大学教育学部講師、助教授を経て、2001年教授。2017年4月より学部長。
専門種目は体操競技。大学では器械運動ならびにゴルフの専門の授業を担当している。ゴルフは30歳前後から始め、継続して実施してきており、東海地区では大学ゴルフ研究会が30年以上継続して実施されており、その幹事を務めている。50歳を期にクラブのメンバーとなり、本格的にゴルフに取り組み、現在HC3となっている。
HCを維持するために、ラウンドと練習を継続しているが、最近は多忙のため中々時間が取れないのが現状である。
研究分野はスポーツ心理学。大学では体育心理学を専門の授業として担当している。専門はメンタルトレーニング、イメージトレーニングであり、選手の心理面のサポートも実施している。
所属学会は日本体育学会、東海体育学会、日本スポーツ心理学会、日本ゴルフ学会である。東海体育学会では会長、日本ゴルフ学会では理事を務めている。また、免許更新講習において、「学校教育におけるゴルフ取り上げ方と活動の工夫」を実施し、ゴルフの理論とともにスナッグゴルフを用いて講習を実施している。※この記事は掲載元(月刊ゴルフ用品界 GEW)の許可を頂いて転載しています。
掲載元 月刊ゴルフ用品界 7月号(見本誌の申し込みはこちらから)
鶴原清志(つるはら・きよし)
1956年福岡県生まれ。1979年筑波大学体育専門学群卒業。1984年筑波大学体育科学研究科(博士課程)中退。1984年名古屋大学総合保健体育科学センター助手。1986年三重大学教育学部講師、助教授を経て、2001年教授。2017年4月より学部長。
専門種目は体操競技。大学では器械運動ならびにゴルフの専門の授業を担当している。ゴルフは30歳前後から始め、継続して実施してきており、東海地区では大学ゴルフ研究会が30年以上継続して実施されており、その幹事を務めている。50歳を期にクラブのメンバーとなり、本格的にゴルフに取り組み、現在HC3となっている。
HCを維持するために、ラウンドと練習を継続しているが、最近は多忙のため中々時間が取れないのが現状である。
研究分野はスポーツ心理学。大学では体育心理学を専門の授業として担当している。専門はメンタルトレーニング、イメージトレーニングであり、選手の心理面のサポートも実施している。
所属学会は日本体育学会、東海体育学会、日本スポーツ心理学会、日本ゴルフ学会である。東海体育学会では会長、日本ゴルフ学会では理事を務めている。また、免許更新講習において、「学校教育におけるゴルフ取り上げ方と活動の工夫」を実施し、ゴルフの理論とともにスナッグゴルフを用いて講習を実施している。※この記事は掲載元(月刊ゴルフ用品界 GEW)の許可を頂いて転載しています。
掲載元 月刊ゴルフ用品界 7月号(見本誌の申し込みはこちらから)

本学の授業風景(緒方貴浩先生)

スナッグゴルフの用具で導入
 舛本直文(ますもと・なおふみ)
1950年広島県生まれ。1973年広島大学教育学部卒、1977年東京教育大学大学院(体育学研究科)修了後、筑波大学体育センター勤務。1981年より東京都立大学を経て首都大学東京。2016年に定年退職後、現在は特任教授としてオリンピックの教育研究に従事。学位:博士(体育科学、1999年筑波大学)。
専門はスポーツ哲学、スポーツ映像研究、オリンピック研究。現在は、「(自称)オリンピズムの伝道師」としてオリンピック・パラリンピック教育への支援やオリンピックの平和運動の一環として人権啓発関係の仕事に従事している。NPO法人日本オリンピック・アカデミー副会長(研究委員会委員長)等を務める。
主著に『オリンピックのすべて』(2008年訳著、大修館書店)等。
所属学会は、日本体育学会体育哲学専門領域、日本体育・スポーツ哲学会(理事)、日本スポーツ社会学会、日本スポーツ学会(運営理事)、日本ゴルフ学会(関東支部副支部長)、国際スポーツ哲学会、国際オリンピック史家学会等。
東京都立大学時代からゴルフの授業を担当。公開講座のゴルフ指導も担当し、公開講座修了生の自主グループ「トカレゴルフ?楽部」の顧問として指導している。現在は、玉川大学の非常勤講師としてゴルフの授業を担当している。※この記事は掲載元(月刊ゴルフ用品界 GEW)の許可を頂いて転載しています。
掲載元 月刊ゴルフ用品界 6月号(見本誌の申し込みはこちらから)
舛本直文(ますもと・なおふみ)
1950年広島県生まれ。1973年広島大学教育学部卒、1977年東京教育大学大学院(体育学研究科)修了後、筑波大学体育センター勤務。1981年より東京都立大学を経て首都大学東京。2016年に定年退職後、現在は特任教授としてオリンピックの教育研究に従事。学位:博士(体育科学、1999年筑波大学)。
専門はスポーツ哲学、スポーツ映像研究、オリンピック研究。現在は、「(自称)オリンピズムの伝道師」としてオリンピック・パラリンピック教育への支援やオリンピックの平和運動の一環として人権啓発関係の仕事に従事している。NPO法人日本オリンピック・アカデミー副会長(研究委員会委員長)等を務める。
主著に『オリンピックのすべて』(2008年訳著、大修館書店)等。
所属学会は、日本体育学会体育哲学専門領域、日本体育・スポーツ哲学会(理事)、日本スポーツ社会学会、日本スポーツ学会(運営理事)、日本ゴルフ学会(関東支部副支部長)、国際スポーツ哲学会、国際オリンピック史家学会等。
東京都立大学時代からゴルフの授業を担当。公開講座のゴルフ指導も担当し、公開講座修了生の自主グループ「トカレゴルフ?楽部」の顧問として指導している。現在は、玉川大学の非常勤講師としてゴルフの授業を担当している。※この記事は掲載元(月刊ゴルフ用品界 GEW)の許可を頂いて転載しています。
掲載元 月刊ゴルフ用品界 6月号(見本誌の申し込みはこちらから)
 ゴルフ授業は、「スポーツ科学演習」として、西宮上ケ原キャンパスの第2フィールドと近隣の上ケ原ゴルフ練習場を使用して授業が展開されていました。私は2004年度からゴルフ授業を担当し、その後、神戸三田キャンパスの理工学部と総合政策学部の教員からの強い要望もあり、神戸三田キャンパスでもゴルフ授業を展開することとなりました。
その神戸三田キャンパスには、12打席、90ヤードの立派なゴルフ練習場(写真参照)とゴルフアプローチ兼アーチェリー場(150ヤードのショートコース)があり、全国でもこれほど充実したゴルフ施設がある大学はないのではないかと思われます。
しかし、2008年度に人間福祉学部が開設されて以来、私達スポーツ科学・健康科学研究室のメンバーは、人間福祉学部とスポーツ科学・健康科学教育プログラム室を兼任し、ゴルフ授業は、神戸三田キャンパスで開講される「体育方法学演習C」の中で2回ほど実施する程度となりました。
ゴルフ授業は、「スポーツ科学演習」として、西宮上ケ原キャンパスの第2フィールドと近隣の上ケ原ゴルフ練習場を使用して授業が展開されていました。私は2004年度からゴルフ授業を担当し、その後、神戸三田キャンパスの理工学部と総合政策学部の教員からの強い要望もあり、神戸三田キャンパスでもゴルフ授業を展開することとなりました。
その神戸三田キャンパスには、12打席、90ヤードの立派なゴルフ練習場(写真参照)とゴルフアプローチ兼アーチェリー場(150ヤードのショートコース)があり、全国でもこれほど充実したゴルフ施設がある大学はないのではないかと思われます。
しかし、2008年度に人間福祉学部が開設されて以来、私達スポーツ科学・健康科学研究室のメンバーは、人間福祉学部とスポーツ科学・健康科学教育プログラム室を兼任し、ゴルフ授業は、神戸三田キャンパスで開講される「体育方法学演習C」の中で2回ほど実施する程度となりました。

打席が多いため、2名で1打席使用できる充実した授業環境

関西学院大学准教授
溝畑 潤

東京経済大学 樋口和洋 特任講師

ナイスショット!

いざコースへ!

中央大学 森 正明教授

ゴルフ実習コンペ日の夕食を兼ねたパーティー
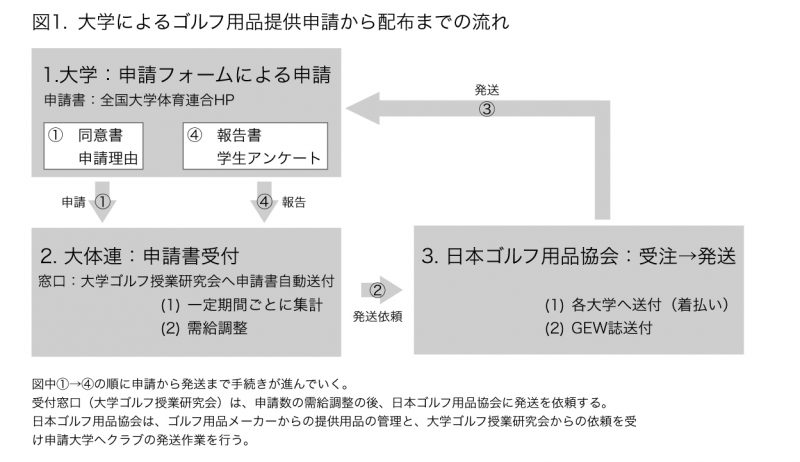
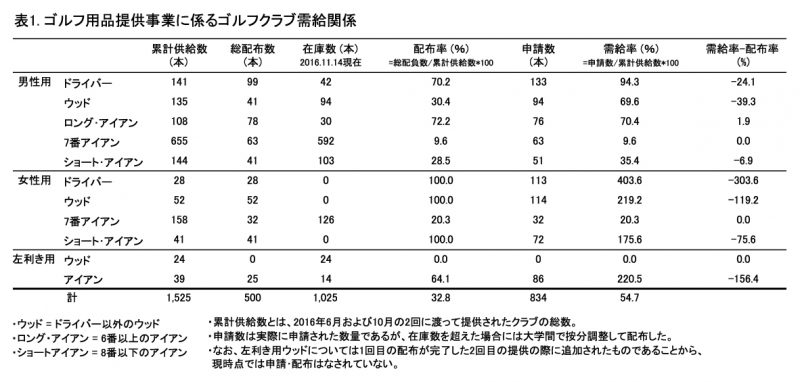
 以上
髙𣘺 宗良(たかはし むねよし)
1969年東京都生まれ。
博士(教育学)、博士(保健学)。
鎌倉女子大学児童学部准教授、武蔵野美術大学兼任講師。
専門は、スポーツ方法学、安全教育学。
安全教育学と授業改善の視点からゴルフについて研究をしている。
日本ゴルフ学会理事・関東支部理事長、大学ゴルフ授業研究会世話人。
日本運動・スポーツ科学学会理事。
(公財)日本水泳連盟学生委員会関東支部副支部長、地域指導者委員会委員。
三鷹市スポーツ推進審議会委員。
以上
髙𣘺 宗良(たかはし むねよし)
1969年東京都生まれ。
博士(教育学)、博士(保健学)。
鎌倉女子大学児童学部准教授、武蔵野美術大学兼任講師。
専門は、スポーツ方法学、安全教育学。
安全教育学と授業改善の視点からゴルフについて研究をしている。
日本ゴルフ学会理事・関東支部理事長、大学ゴルフ授業研究会世話人。
日本運動・スポーツ科学学会理事。
(公財)日本水泳連盟学生委員会関東支部副支部長、地域指導者委員会委員。
三鷹市スポーツ推進審議会委員。